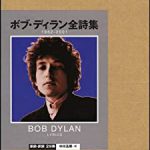以前、ブラウザ・アプリゲームの『アイドルマスターシャイニーカラーズ(通称シャニマス)』内に登場する洋楽の元ネタをSpotifyにまとめ、かつ楽曲に関する記事を書いたことがある。
Sponsored Link
記事:アイドルマスターシャイニーカラーズ(シャニマス)に登場する音楽・洋楽元ネタ
担当の変更が理由なのかは不明だが、リリースから1~2年くらいで洋楽ネタは出てこなくなった。なのでしばらく忘れていたのだが、2023年10月よりWEB連載を開始したスピンオフ漫画『アイドルマスター シャイニーカラーズ 事務的光空記録(通称ジムシャニ)』のサブタイトルで再び洋楽の要素が出てきたので、姉妹記事としてジムシャニ版のページを書くことにした、というのが本記事となる。
Spotify Playlist - Foreign Music in THE IDOLM@STER SHIN COLORS
なおSpotifyでは全て同じ上記のプレイリストに収録している。
概要
謎の新人作家kusomiso……じゃなかった夜出偶太郎先生によるコミカライズ。近年のメディアミックスは明らかにレベルが上がったと感じるが、本作はその中でもかなり秀逸な出来である。まさしく連れてくるべき人を連れてきたという感想だ。
一方でkusomiso先生のpixivアカウントからシャニマス二次創作が一掃されたのはなかなか複雑な気分である。P天界隈なんかは界隈最大手が居なくなったことで阿鼻叫喚なんじゃないだろうか……とかなんとか思っていたら、kusomiso先生が公式で天井努の顔を描いた最初の人間になってしまった。凄い……。司馬遼太郎だと思ってたら本物の歴史学者になっちゃったみたいな感じか。
シャニマスに洋楽要素が出てくるのはしばらくぶりなのだが、これが誰の意向で付けてるのかよく分からない。本編のシナリオライターとして名前が判明している橋元優歩が音楽ライター出身なので本編もジムシャニも音楽要素はこの人が噛んでいる様な気がするのだが、憶測の域を出ない。それともkusomiso先生なんだろうか?
タイトル以前に作品内容もkusomiso先生がどこまで関与してるのか分かんないんだよね。シャニソンこと「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」がリリースされた関係で、はづきさんの年齢が公式で初めて分かるんだけど
これ見るにどうもkusomiso先生は、はづきさんの年齢知らされてなかったっぽいんだよな。公式コミカライズしてるんだから、主人公の基本的なプロフィールくらい伝えておけよ高山!
各話サブタイトル
1st page : A day in the life
ビートルズ(The Beatles)のアルバム「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)」の最後に収録された同名タイトルから。
いきなりビートルズ(The Beatles)という世界一有名なバンドの曲を持ってきたわけで、「サブタイトルは洋楽のタイトルで行くぜ」という意図を読者側に伝える意図を感じる。
サージェント・ペパーズ~は史上初のコンセプトアルバムとされる記念碑的作品であると同時に「架空のバンドの作品(という設定)」とされていることも興味深い。「アイドルマスターという架空のアイドルを扱う作品に付けた」とするべきか、それとも「八雲なみになろうとする七草にちかに付けた」とするべきか。
2nd page : sugarcube
ヨ・ラ・テンゴ(Yo La Tengo)の同名曲からで、アルバムの「I Can Hear the Heart Beating as One」に収録されている。
Whatever you want from me
Whatever you want I'll do
Try to squeeze a drop of blood
From a sugarcube
タイトルと歌詞に登場するsugarcubeという単語と周辺のフレーズは「get blood from a stone」という英語の慣用句に由来している。「You can't get blood from a stone」で「無い袖は振れない」という意味だ(参考:英辞郎 on the WEB:「get blood from a stone」)。
石から血が採れないように角砂糖からも血は採れない、というわけだが、stoneではなくsugarcubeなのは後半の歌詞にも掛かっている。
And though I like to act the part of being tough
I crumble like a sugarcube for you
タフ(TOUGH)な男でいるフリをしたいけど、角砂糖の様に崩れ去っていくんだ……という歌詞っす。冬優子ちゃん、これ意味分かんないっす。忌憚のない意見ってやつっす。
3rd page : Little sister, the sky is falling…
3話目にして少し変化球。曲のタイトルではなく、パティ・スミス(Patti Smith)の『Kimberly』の歌詞から。キンバリーはパティ・スミスの妹の名前なのだが、これだと意味分かんないもんな。キンバリーは大崎姉妹と違って13歳も年が離れた妹で、歌詞は主に彼女が産まれた時のことを歌っている。姉が妹にというより母親が娘に語りかけるような印象の歌詞である。
Little sister, the sky is falling, I don't mind, I don't mind
Little sister, the fates are calling on you
『the sky is falling』は「破滅が近づいている」とか「もう終わりだ」という意味合いの慣用句。要約すると「ひぃん!……な、なーちゃん助けて……」みたいな感じか。原作やると実際の甜花ちゃんはイメージよりかなり「お姉ちゃんしてる」わけですが……。
4th page : All is full of love.
ビョーク(Björk)の同名曲から。歌詞の主旨は「あなたの周りはあなたが気付いていないだけで、愛で満たされている」という感じの内容。4話目は色々な意味でシャニマス本編に近いテーマを扱っている(やっぱりストレイライトを書くと「己と向き合う」要素が入るんだろうか)のだが、終盤のはづきに対する回答がこのタイトルなら救われていると考えるべきだろうか。
自分ならシュレッダーで分断された文字をもう一度繋ぎ直すあたりで、ウィリアム・バロウズ(※1)とか、『スティーリー・ダン(Steely Dan)』(※2)とかを連想するかなぁ……。えっ?そういうコメント要らない?
※1:「既に出来上がった文章の切り貼りで新しい文章を作る」カットアップという特殊な手法で作品を作る作家。音楽方面にも影響を与えた。
※2:サンプリングや切り貼りの編集が執拗というか冷酷(ベテラン演奏家に1フレーズだけ何度も演奏させて、気に入った1回だけ採用したのをツギハギしたりする)なことで知られるバンド。なおバンド名はバロウズの作品から取られている。
ビョークはミュージカル映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク(Dancer in the Dark)』で主演を演じているのだが、この映画が欝映画の代名詞になるくらい強烈だったせいで凄惨な目に遭う主人公セルマのイメージが未だにあるんだよな。現実では超大スターなんだけど。
5th page : Something for the weekend.
ザ・ディヴァイン・コメディ(The Divine Comedy)の同名曲から。なんかタイトル的に「なんてことのない、いつもの週末」みたいなイメージがあるが、実際の内容は「主人公の男が狙っていた女に家に誘われ、「薪小屋で変な音がするから見てきて」と言われたので覗いたら気絶させられ、気がついたら金も車も盗まれていた」というもの。全然日常じゃなかった。一見日常的に見えて監禁(?)という非日常に巻き込まれるエピソードのタイトルとしてつけた感じかな。
放クラにはづきさんが光の監禁された後、今度は妹の方がシャニPを闇の監禁……という衝撃の構成のエピソードであり、ここで裏主人公として七草にちかが顔見せをして単行本1巻が終了する。とんでもねぇ漫画だな……。
5.5th page : Canned Heat
ジャミロクワイ(Jamiroquai)の同名曲から。一応『キャンド・ヒート(Canned heat)』ってバンドも存在するんだけど、曲名縛りだろうから多分こっち。どちらにせよ、本エピソードで断片的に示される「にちかが内包したアイドルへの憧憬と切実さ」を見事に示した引用だ。
ジャミロクワイは実質的にジェイ・ケイのソロユニットで、バンド名は音楽用語のジャム(Jam)とアメリカ先住民のイロコイ部族(Iroquois)を組み合わせたものなのだが、イロコイのスペルをミスってjamiroquaiになったというしょうもないエピソードがある。加えてネイティブアメリカンの格好をしながら環境の危機を訴える(なにせ1stアルバムのタイトルが『Emergency of the Planet Earth』だ)スタイルにもかかわらず、ジェイ・ケイ本人は環境に悪いスーパーカーが大好き、という人間の業を感じる振る舞いで色々言われていた人物でもある。
なんかしょうもないエピソードばっかり書いてしまったが、アシッドジャズ(Acid Jazz)を牽引する、90年代を代表するバンドであるのは間違いない。なにせ3rdアルバム『トラベリング・ウィズアウト・ムービング(Travelling Without Moving)』(冒頭の代表曲『ヴァーチャル・インサニティ(Virtual Insanity)』が有名)が全世界で800万枚以上を売り上げて「世界でもっとも売れたファンクアルバム」としてギネスに登録されたのだから。……でも、やっぱりちょっと言いたくなるよなあ?
6th page : The Kids Are Alright.
ザ・フー(The Who)のデビューアルバム『マイ・ジェネレイション(My Generation)』収録の同名曲から。バンドや本アルバムとともにモッズ(※)のアンセムとして知られ、1979年に公開されたザ・フーのドキュメンタリー映画のタイトルとしても使われている。
(※)モッズ(Mods)はModernistに由来する単語で、1950~60年代のイギリスの若い労働者階級に流行した音楽やライフスタイル、およびその支持者を指す言葉。
ビョーク、ディヴァイン・コメディ、ジャミロクワイと割と新しめ(ロック界においては90年代は「新しめ」なのである……)なのが続いたな、と思ったら白人ロック第1世代みたいな時代に逆戻り。
要約すると「ここから出ていかなきゃ。あの娘はアイツらに任せよう。大丈夫、アイツらは良い奴さ(= The Kids Are Alright)」というような歌詞なのだが、妹と距離を置くこととなったはづきの心境と重なるところがあるだろうか?
本エピソードで「(この時点で)283プロでWINGを優勝したユニットは居ない」ことが明言される。アニメ版で初期4ユニットが優勝していないのでほぼ分かっていたことではあったから驚きはないが、「WINGを優勝しないとアイドルを続けられない」というにちかの課せられた条件の解像度上がるんだよな。ここで原作で摩美々がWING優勝逃したときのエピソードを拾ってくるのだが、この作品は原作のこういう要素の取り上げ方がべらぼうに上手い。
7th Page:Anthems for a Sixteen Year-Old Girl
タイトル見て「よくこんなドンピシャなタイトル見つけたな!」と思ったのだが、実は元ネタでは「Seventeen」のところを、にちかに合わせて「Sixteen」にしている。元ネタはカナダのバンド、ブロークン・ソーシャル・シーン(Broken Social Scene)のAnthems for a Seventeen Year-Old Girlから。
歌詞なのだが、同じフレーズを何回も何回も繰り返す(なにせ最大15回位繰り返したりする)ので、その限られたフレーズからの解釈にはバラツキが出る曲である。なんか曲名だけ見て「パパとママは反対するけれど、これがアタシたちティーンのロックだ!」系の曲かと思ったのに全然違った。なんかもっと遠くから見ている歌詞だよね。
Sponsored Link
「八雲なみ」がsixteen year-old girlであるにちかにとってのAnthemであることを描写した上で、その八雲なみを通じて物語の視点は過去へ。そしてここでなんとアイドルマスターシャイニーカラーズ、リリースから約6年余りを経て、天井努の初の顔出しである。マジで変な声出てしまった。
なお識者によると「アイドルマスターのプロダクション社長は本編では黒塗りで登場するが、スピンオフで過去編になると顔が描かれるようになる」という法則があり、高木社長(765プロ)と黒井社長(961プロ)も過去編となる『朝焼けは黄金色 THE IDOLM@STER』で初めて顔出しをしているらしい。してみると伝統に則ったお披露目だったわけだ。
8th Page:Ballet Mécanique
ここまで洋楽で来たが、ここでなんと邦楽。とはいえ後述するようにルーツもコンテクストも過去一複雑な楽曲である。坂本龍一の「未来派野郎」(1986年)に収録された同名曲「Ballet Mécanique」が元ネタ……と、取り敢えずしておこう。
まず、20世紀前半に活躍した芸術家フェルナン・レジェによって制作された実験映画「Ballet Mécanique」(1924年)があり、坂本龍一の曲はこの映画の「機械が踊る」コンセプトの影響を受けた作品となる。作中で天井が上司から譲り受けた餞別(ゼンマイ仕掛けのバレエ人形)が象徴するように、八雲なみが己の意志とは裏腹に天井(と芸能界の現実)の元で操り人形のように振る舞う他なかった事実を見事に表したタイトルである。
これだけでも凄いのだが、本タイトルは更に重要なコンテクストを含む。実は本曲は元々坂本龍一が岡田有希子に提供した曲「Wonder Trip Lover」を編曲して歌詞を変えたセルフカバー曲なのである。岡田有希子は一世を風靡しながら1986年に18歳の若さで自殺したアイドルで、死後若者を中心に後追いする人間が続出し「ユッコ・シンドローム」として社会問題となった。
従って本タイトルは「機械仕掛けのバレエ人形のようだった八雲なみ」と「超新星のように輝きながらも、ある日突然消え去った実在のアイドル岡田有希子」という二つの含意を含んでいることになる。ここまでで色々なコンテクストが有ったと思うが、今回のは相当な衝撃を感じた。
9th Page:This Must Be the Place
トーキング・ヘッズ(Talking Heads)の同名曲「This Must Be the Place (Naive Melody)」が元ネタ。5thアルバム「Speaking in Tongues」の最後に収録されている。ちなみに最初に収録されている「Burning Down the House」もトーキング・ヘッズを代表する有名曲で、『ジョジョの奇妙な冒険』のエンポリオのスタンド「バーニング・ダウン・ザ・ハウス」はこれが元ネタだし、バンド自体がティッツァーノのスタンド「トーキング・ヘッド」の元ネタだ。
トーキング・ヘッズは美大出身者が中心となったインテリバンドでひねくれた内容の曲が多いのだが、本曲は彼らには非常に珍しいラブソング。デヴィッド・バーンは「普段変わった曲ばっかり作っている自分が他の人間と同じようにラブソングを作ったら陳腐な物になってしまう」と踏んで曲を作ったという主旨の発言を行っており、意識的に素朴で純真で不器用なメロディを曲中に入れる工夫を行っている。これが曲名の最後に付いている副題「Native Melody」の所以となる。
Home is where I want to be
But I guess I'm already there
I come home, she lifted up her wings
I guess that this must be the place
WING優勝に失敗しながらも美琴と共に283プロでアイドルを続けることとなったにちかにふさわしいタイトルだが、空や翼をモチーフにすることが多いシャニマスのイメージにピッタリな「she lifted up her wings」というフレーズがあることにも着目したい。見事な曲選定だ。
9.5th Page:Island in the Sun
ウィーザー(Weezer)の同名曲。バンド名はボーカルでありながら喘息持ちのリヴァース・クオモ(Rivers Cuomo)が、「喘息の際に呼吸で引き起こされる甲高い口笛のような音(=weezer)」から付けた。
曲は3rdアルバム「Weezer (The Green Album)」に収録。The Green Albumってなによって感じだが、実は1stのタイトルもWeezerでジャケットのカラーから副題が実質的に付けられており、1stの方はThe Blue Albumと呼ばれる。ちなみに6thアルバムは同じ要領で「Weezer (The Red Album)」だ。
ビーチボーイズ(The Beach Boys)を想起させるような休日を歌ったポップソングのようでありながら、どこかで哀愁も漂う。はづきさんが旅行に行く本エピソードに合致した曲だ。幕間となる番外編であるが、最後にルカマネが台詞と後ろ姿だけ出てきて、みこルカ界隈を大きく震撼させたのである……。えっ?私だけですか?
10th Page:Girls Just Want to Have Fun
シンディ・ローパー(Cyndi Lauper)の同名曲が元ネタ。ソロシンガーとしてデビューした際に初めて出したシングル曲で、ソロ1stアルバムの「She's So Unusual」(1983年)に収録されている。爆発的にヒットし、女性の奔放さを鼓舞する内容とシンディの奇抜なファッションが当時のアメリカ人女性に大きく影響を与えた。
余談だがシンディは『We Are the World』(1985年に収録)にも参加しており、何も知らない人があの有名な動画を見たとき「なんか妙にケバい金髪のお姉ちゃんが凄え印象的な歌い方してるな……?」と思うシーンがあると思うのだが、それがシンディ・ローパーである。ちなみにこの収録時ジャラジャラつけたアクセサリーの音をマイクが拾ってしまうのでスタッフに怒られるという、いかにも彼女らしいエピソードがある。
本曲は元々はロバート・ハザード(Robert Hazard)が自身のバンドの為に作った物を、許可を経てカバーしたものとなる。英語の曲は「主人公がheで相手がgirl」の曲を女性が歌うときに、性別を入れ替えて「主人公がsheで相手がboy」で歌うことがよくあるのだが、元のハザード版もgirlsではなくboysだった。シンディ・ローパー版のイメージが圧倒的となった現在からすると全然想像つかない。
ちなみに歌詞にworking dayとあるので主人公は明らかに成人済みである(学生ならschool dayになるはず)。加えてシンディも新人じゃなくてその時点でアラサーだった。girl……?となるが、当時の邦題はそんなことは無視して「ハイスクールはダンステリア」という、明らかに女子高校生を想像させるタイトルだった。時代ですねぇ。
女性アイドルを扱う作品にストレートに刺さる曲が来たなぁという感じ。今回のヒーローとなる雛菜、そして雛菜が大事にしたファンにもピッタリのチョイスだ。もっとも「当時この曲に勇気づけられた女性たちにあった葛藤のようなもの」って、市川雛菜にカケラもない気もするけれど……。時代と言うべきか、市川雛菜の人間強度が凄まじすぎると言うべきか。
11th Page:Champagne Supernova
オアシス(Oasis)の「シャンペン・スーパーノヴァ(Champagne Supernova)」が元ネタ。2ndアルバム「(What's the Story) Morning Glory ?」のラストに収録されている。
おそらく初めてシャニマス本編(enza版)での洋楽ネタとニアミスである。enza版シャニマスの洋楽ネタの記事でも扱ったとおり、2ndアルバムの収録曲でありアルバムのタイトルにもなっているMorning Gloryが
上記の通り樹里のサポートカードとして引用されている。こちらは放クラのカードだが、ジムシャニのほうはSupernovaという天体用語の方に着目したのか、イルミネにスポットが当たった話となっている。しかし、にちかと美琴の関係を食変光星に例えるセンスは震え上がるくらいシャニマスしてるなぁ。
なお、作詞したノエル・ギャラガー(弟でありボーカル担当でもあるリアムと喧嘩ばっかりしていることで有名)によるとタイトルのChampagne Supernovaはなにかの聞き間違いで覚えていたフレーズで特に意味のある言葉ではないらしい。
そういえばオアシスで思い出した。アイドルマスターシリーズの先輩であるシンデレラガールズに「夢見りあむ」なるキャラがいて、姉がいて自分と同じくキラキラネームだと明言しているのだが、やっぱり名前「夢見のえる」なんだろうか?
12th Page:Somebody to Love
本記事最大の危機(?)である。なんと同名曲が2つあり、なんかどっちとも取れるような……?候補となる曲は
- Queen『Somebody to Love』
- Jefferson Airplane『Somebody to Love』
の2つであり、前者の方が圧倒的に有名で洋楽知らない人でも知ってる様な曲なのでこっちの話題ばっかり見るのだが、自分は個人的に好きな後者の曲を先に想像してしまった。逆張りかもしれない。
取り敢えずQueenのSomebody to Loveから。前話のChampagne Supernovaも有名な曲持ってきたなぁと思ったが、この曲はもう有名のレベルが違いすぎて解説必要なのか?って感じだ。
5thアルバム『A Day at the Races』収録。このアルバムには伝説的シミュレーションゲーム、タクティクスオウガの副題として引用されたLet Us Cling Together(邦題は「手をとりあって」)も収録されている。そして精神的な続編のファイナルファンタジータクティクスの最終章タイトル「愛にすべてを」も本曲Somebody to Loveの邦題だ。(オウガバトルサーガは松野泰巳の趣味でQueenネタばっかりなので言い出したらキリが無い)
コーラスと併走するような盛り上がりを見せる曲であるが、内容は悲壮な物で「神を信じてずっと生きていた。毎朝死ぬ気で起きて、一生懸命働いているけど、なんの救済も無かった!周りはみんな自分にイカれているとか言ってくるんだ!誰か愛する人を見つけてくれ!」って感じの内容。
I get down (down) on my knees (knees)
And I start to pray
'Til the tears run down from my eyesLord, somebody (somebody), ooh somebody
(Please) can anybody find me somebody to love?
跪いて神に祈ったのに報われることが無かった、という主旨がルカの持ち曲である「神は死んだ」と非常にマッチしてますよね~って、じゃあ正解こっちじゃないのか?
一応、推し(?)のジェファーソン・エアプレイン(Jefferson Airplane)の方も挙げてみよう。当時のサイケデリック文化を代表するバンドの一つで、1960年代後半に最盛期を迎えた。ロックファンにとっては伝説的ライブであるウッドストック(1969年)にも参加しており、本曲はそこでも歌っている。と言うわけで、一応バンドも曲もこっちの方が先輩というわけだ。
When the truth is found to be lies
And all the joy within you dies
リード・ボーカルのグレイス・スリック(Grace Slick)が女性で、その力強いボーカルからいきなり始まる曲なのだが、出だしのこの歌詞が凄い好きだ。
ヒッピー文化直下の曲で、アメリカ全土に共産主義への嫌悪があり(なので歌詞に「red」が出てくる)、という時代と目線の曲であることを前提に「この世の何もかもが不信に感じたとき、愛する誰かが欲しいとは思わない?そういう相手を早いとこ見つけた方が身の為よ」という主旨の曲となる。……なんか自分で書いててQueen説強くなったかもしれない(←オイ!)。でも上記で引用した冒頭のフレーズは斑鳩ルカそのものなんだよなぁ。
権利問題でバンド名がJefferson Airplane→Jefferson Starship→Starshipと変わっていったんだけど、この辺の難しさが無かったら、ナランチャのスタンドだってエアロスミス(Aerosmith)じゃなくて、こっちだったかもしれないのに……。と、ここまで考えて雑誌掲載時にプッチのスタンドがレッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)のステアウェイ・トゥ・ヘブン(Stairway to Heaven)だったのに、権利問題でQueenのメイド・イン・ヘブン(Made in Heaven)に変わったのを思い出した。
Led Zeppelinって自分たちは他人の曲パクりまくるくせに、勝手に自分の名義付けた後はそういうことにウルサいんだよな……。ビッグ・オーの件もそうだけど、ブライアン・メイ(Brian May。Queenのギタリスト)はこの辺の懐が違うな。まッ、そんなワケで変なところで接点が出来ましたね!(←ホントか?)
まぁどっちでも良いんですが9.5話でチラ見せしたルカマネがばっちり顔出しで登場。冒頭の社員教育用ビデオでは隈が無いのに現在時間軸だとハッキリと隈が描写されていることに戦きながらページを進めていったら、サブタイトルの「somebody to love」が、本作でもっとも堂々と見開きで書かれていたのです……!(震え)。これもう「アイドルマスター kusomiso colors」だよ……。
終わりに
原作の方に比べて新しめの楽曲の採用が多いという印象である。元々ロックというジャンル自体が衝動であるとか性欲であるとか暴力的なものを表現に昇華している部分があり、かつての洋楽ロックを元ネタにするのは、シャニマスのイメージとはそぐわないところもあるなぁという感想もあった(ので、余計に「ライターの趣味由来でやってるよなぁ」と思ったわけだ)。こちらは女性ボーカルの曲を採用したりして、本編イメージに近づいている感がある。おかげで調べるの結構大変だ。ビートルズとかザ・フーなんかは結構スラスラ書けるんだけどなぁ。
関連記事
Sponsored Link